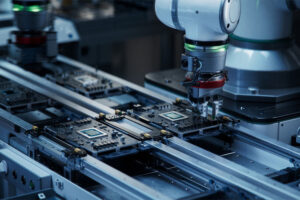※当ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
NVIDIAのGPUには、「Tensorコア」と呼ばれるAI処理専用の演算ユニットが搭載されています。
とくに最新のBlackwellアーキテクチャでは、このTensorコアが大幅に再設計され、パフォーマンスと柔軟性が飛躍的に進化しています。
今回はTensorコアの基本的な役割から、4000番台(Ada Lovelace世代)との違い、Blackwellで何がどう強化されたのかを技術的な観点からわかりやすく解説します。
Tensorコアとは何か
Tensorコアとは、主にAI計算や深層学習の高速化を目的として設計された専用演算ユニットです。
NVIDIAはVolta世代(V100)からTensorコアを導入しており、行列演算(マトリクス演算)を効率的に処理する能力に特化しています。
通常のCUDAコアでは、複雑な行列積を計算するには多くの命令とクロックサイクルが必要になります。
しかしTensorコアは、行列A×行列B=行列Cといった乗算加算(FMA:Fused Multiply Add)を、1サイクルでまとめて並列実行できるよう設計されています。
この仕組みにより、AI推論や学習処理における速度が桁違いに向上しているとのこと。
4000番台におけるTensorコアの特徴
RTX 4000番台(Ada Lovelaceアーキテクチャ)に搭載されたTensorコアは、第4世代にあたります。
この世代では、主に以下のような改良が加えられました。
・FP8(8bit浮動小数点数)による高効率なAI演算サポート
・構造化スパース(sparse)演算への最適化
・DLSS 3の推論処理における高速化
推論やトレーニング時に使用される行列計算の処理量が大幅に向上し、より多くのAIモデルをリアルタイムで処理できるようになりました。
ただし4000番台のTensorコアは、演算性能の向上こそあるものの、対応データ型の種類や柔軟性には制限がありました。
BlackwellアーキテクチャでのTensorコアの進化
最新のBlackwellアーキテクチャでは、第5世代のTensorコアが搭載されています。これまでの世代を大きく上回る柔軟性と汎用性を備えており、次のような技術的進化が確認されています。
1. FP4/INT4対応によるさらなる高効率化
Blackwell世代では、従来のFP8に加えて、さらに小さなFP4(4bit浮動小数点)やINT4(4bit整数)といった低精度演算に対応しています。
低精度でも一定の精度を保てるAIタスクにおいては、演算回数が大幅に減るため、実行速度がさらに向上します。
これは推論タスク、とくにリアルタイム性が重視される音声認識や画像分類で大きな効果を発揮します。
2. 動的スパース性の強化
Blackwell Tensorコアは、従来よりも柔軟なスパース行列演算に対応しています。
使用していない(ゼロが多い)パラメータをより効率的に除外し、電力消費と演算負荷を抑えつつ、学習・推論を高速化します。
とくに大規模言語モデル(LLM)や生成AIの処理において、メモリ帯域と処理負荷の軽減が顕著ですね。
3. データ型の混合処理に対応
BlackwellのTensorコアは、FP16、BF16、FP8、FP4、INT8など、複数のデータ型をタスクに応じて混在処理できるように進化しました。
柔軟なモデル最適化が可能となり、トレードオフを最小限に抑えた運用が可能です。
たとえば、計算精度が求められる部分にはBF16を使い、省エネが求められる部分ではFP4を用いるといったアプローチが実用レベルで実装できるようになります。
実際の性能差はどれくらいか
NVIDIAが公開している初期ベンチマークによれば、Blackwell世代のTensorコアは、前世代比で最大2倍以上のAI推論性能向上を記録しています。
また、低精度演算(FP4)を活用した場合には、電力効率が最大5倍改善されたという報告もあります。
DLSSや生成AIだけでなく、エッジコンピューティングやビジュアル処理にも恩恵があり、汎用性の面でも大きな飛躍が見られます。
Tensorコアが単なるAI演算ユニットにとどまらず、GPU全体の計算構造を変える「中核要素」となりつつあることを意味していますね。
これからのGPU選びにおいては、Tensorコアの進化が「何ができるか」だけでなく、「どれだけ効率よくできるか」を左右する重要な指標となるでしょう。
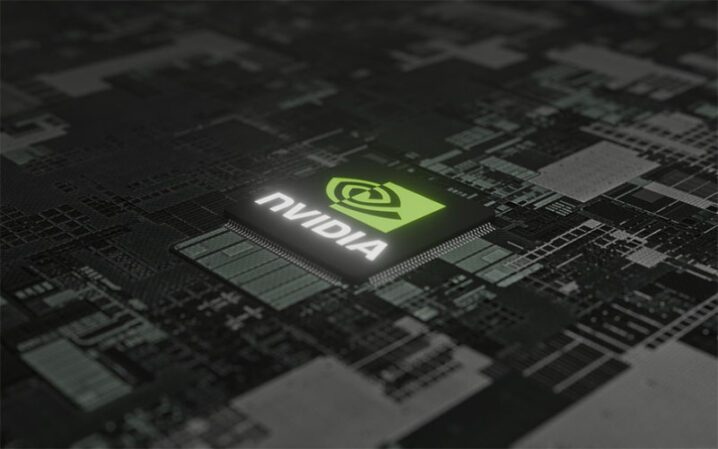
 コスパ最強!BTOパソコンおすすめランキング 2024年版
コスパ最強!BTOパソコンおすすめランキング 2024年版 BTOパソコンが安い時期を調査
BTOパソコンが安い時期を調査