※当ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
Windows 10の公式サポート終了が2025年10月14日に迫る中、「Windows 11への移行はまだ考えていない」という方も多いのではないでしょうか。
そんなユーザーにとって注目したいのが、Microsoftが提供する延長セキュリティ更新プログラム「ESU(Extended Security Updates)」です。
この記事では、ESUとは何か、その利用条件や価格、内容について詳しく解説します。Windows 10を長く使い続けたい方にとって、必見の情報です。
Windows 10を長く使うための「ESU」とは
「ESU(Extended Security Updates)」は、Microsoftが提供する有償の延長セキュリティ更新プログラムです。
Windows 10の公式サポートが終了した後も、特定の条件を満たすことでセキュリティ更新を受け取ることができます。
サポート終了後に発見される新たな脆弱性やセキュリティリスクに対応するため、Windows 10を安全に使い続けるための重要な選択肢となっています。
特に、Windows 11への移行を急ぎたくない企業や、現在のWindows 10環境をできるだけ長く維持したい個人ユーザーにとって有用なサービスです。
ESUを利用することで、移行準備に必要な時間を確保しつつ、セキュリティのリスクを最小限に抑えることができます。
ESUを使うための条件
ESUを利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、ESUはすべてのWindows 10エディション(Pro、Enterprise、Homeなど)で利用可能です。
ただし、利用するには、Windows 10のバージョンが「22H2」以降であることが必須条件となっています。
古いバージョンのWindows 10を使用している場合は、まず「22H2」にアップデートしておきたいですね。
また、ESUはサブスクリプション形式で提供され、有償であることに注意が必要です。
料金は利用年数やエディションによって異なりますが、基本的に企業向けに設計されたプログラムのため、個人ユーザーにとってはコストがやや高くなる場合があります。
具体的には、個人ユーザー向けは年額30ドル(約5,000円)です。 5000円を支払うことで、2025年10月14日の公式サポート終了後も、1年間にわたり重要なセキュリティ更新を受け取ることができます。
ただし、ESUはセキュリティ更新のみを対象としており、新機能の追加やバグ修正、テクニカルサポートは含まれません。
また、個人向けESUは1年間のみの提供で、法人向けのような2年目以降の延長オプションはありません。
Windows12までの延命は現実的か?
2025年1月時点では、次世代のWindows、つまりWindows12が2025年秋から2026年春に登場すると予想されています。
Windows 10の公式サポート終了が2025年10月14日ですから、そこからESUで1年間延命したとして、デッドラインは2026年秋。
かなりギリギリですが、Windows10からWindows12へスキップできそうですね。
ただし、新しいOSは登場直後に安定性や互換性の問題が発生することも多く、すぐに移行することにはリスクが伴います。
Windows12が安定するまでWindows10のESUが持てばよいのですが、ちょっと厳しいラインのような気がしますね。
個人的にはメインで引き続きWindows10を使う場合、サブとしてWindows11のPCも用意しておくべきかなと思います。ESUは確かに便利ですが、個人向けはあくまでも「1年限定」のようなので、この点は必ず覚えておきましょう。
(今後、2年目以降も提供される可能性はあります)
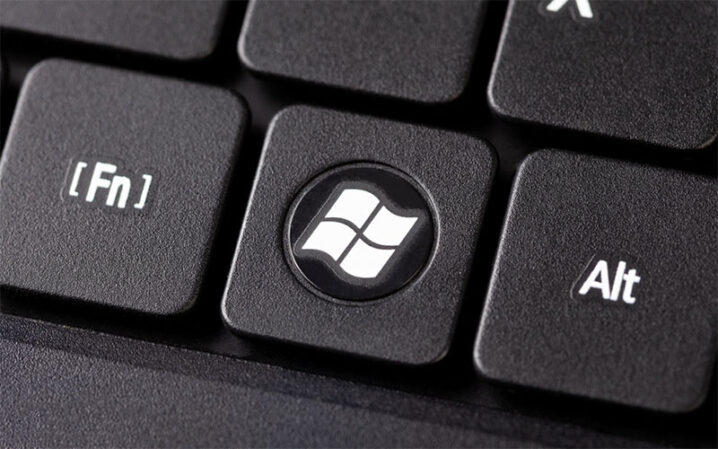
 コスパ最強!BTOパソコンおすすめランキング 2024年版
コスパ最強!BTOパソコンおすすめランキング 2024年版 BTOパソコンが安い時期を調査
BTOパソコンが安い時期を調査











